 |

|
|
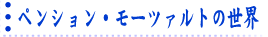 |
 |
 |
 |
サロン・コンサート
 |
山中湖に「ペンション・モーツァルト」という小さなペンションがあって、ここではときどき小さな音楽会が開かれる。先日もバロック音楽の演奏があるというので、晩秋の一日、私は友人たちを誘って出かけた。晴れていれば新雪で飾られた富士山が目近に見えたはずだが、その日は曇っていて、富士を仰ぐことはできなかった。しかし木々の紅葉黄葉は見事で、そういった木々にかこまれた湖畔のペンションで聴く音楽には、都会の音楽会場では味わえない特別の興趣があった。音楽を聴くにはやはりそれにふさわしい環境あるいは雰囲気が必要である。
何百人あるいは何千人を収容する大きなホールで大編成のオーケストラを聴くのもいいものである。しかしそういう場合はどういsても演奏者と聴衆とのあいだの距離が大きすぎて、ともに音楽をたのしむという親密な雰囲気ができにくい。聴衆相互のあいだもそうで、聴衆の数が多ければ多いほど、聴衆はかえって孤独である。だが音楽は本来、心と心を結びつけるもの。一体感のなかでともにたのしむべきものなのである。とくに室内楽はその言葉の通り、小さなサロンで聴いてはじめてその本当のたのしさを味わうことができる。
こういったことから、近頃いろいろな形でサロン・コンサートが催されるようになったのはよろこぶべきことである。ただ、わが国ではサロンというものができにくい。サロンとは、人々が集まって交流し親睦を深める社交の場である。そういうサロンのないところでサロン・コンサートを開いても、それはただ小さな会場での少人数の演奏会というだけのことで、演奏者と聴衆が一緒に音楽をたのしむということにはなかなかならない。この点、都会を遠く離れたペンションでの音楽会となると、一泊をともにする同好の仲間といことで親密な一体感が生まれる。演奏にさきだって演奏者から楽曲や楽器についての詳しい説明をきいたり、演奏のあとで演奏者と聴衆が膝をまじえて何時間でも(夜通しでも)歓談したりすることができるのである。
私は男性数名、女性数名の友人たちと一緒に行ったのだが、演奏のはじまる夜八時、ペンションの狭いホールは四十人ほどの人で一杯になった。曲目と演奏者紹介、また今夜歌われる歌曲の原語と日本語訳を印刷した紙が全員に配られる。これは親切な配慮だった。というのもこの日のプログラムはわが国ではあまり演奏されることのない曲目で、それも歌唱が中心だったからである。その歌唱はカウンターテナーというめずらしいもので、日本人がこの声で歌ったのを聴いたことはこれまでになかった。
演奏にさきだって私たちは音楽史研究の専門家から、バロック音楽、とくに今夜演奏される初期バロック音楽についての簡略ながら有益な解説をきいた。それから演奏になったのだが、演奏のリーダーであるチェンバロの渡辺順生氏も個々の曲目や楽器についての適切な解説をしてくれた。その解説のおかげで私たちは演奏を聴いて大いにたのしんだのだが、これもサロン・コンサートならではのことである。
この日のコンサートは「カウンターテナーと古楽器の世界」と題されていて、出演者はチェンバロの渡辺順生、バロック・ヴァイオリンの渡辺慶子、田崎瑞博、ヴィオラ・ダ・ガンバの宇田川貞夫、それにカウンターテナーが太刀川昭の諸氏である。少人数で聴くのはもったいないような顔ぶれだが、少人数だからこそ音楽はますます高雅に響くことになる。演奏の前に雑談しているとき、「これでは赤字でしょうね」と誰かが言ったのに対して、私と同行していたフランス文学のS氏は「だからこそすばらしいんですよ、黒字になるような会なら私は来ませんよ」と言った。演奏者も主催者も採算は度外視しているのである。
それにしても、こんなのびやかで艶のある、朗々たる高い男声があるとは知らなかった。カウンターテナーというのはテナーよりもいっそう高い男声で、一種の裏声だということだが、とにかくめずらしい。そのめずらしい声で太刀川氏はモンテヴェルディやパーセルやヘンデルのアリアをたっぷり聴かせてくれた。たっぷり、と言うのは量的にたくさんということではなく、質的に聴く者を深く魅了したということである。たんにめずらしかったということではない。歌唱そのものがまことにすばらしかったのである。
器楽がまたよかった。古い音楽をその時代の楽器で、という古楽器演奏は近時ヨーロッパで盛んにおこわれており、来日したドイツのアンティカ・ケルンとか、イギリスのホグウッドの率いるエンシェント合奏団などを私も聴いたことがあるが、山中湖でこの夜に聴いたアンサンブルは、正確さにおいてはこれら西欧の名門グループには及ばないにせよ、音楽に熱中するよろこびの昂揚をもって古雅の調べを湖畔のしじまに響かせ、聴く者を興奮と陶酔にひきいれたのである。音楽とは正確さではない、よろこびであり陶酔である。バロック初期の十七世紀の音楽、それは「バッハを含めてそれ以後のすべての音楽はそれの余韻にすぎないような最も偉大な音楽」だと渡辺順生氏が解説のなかで言っていたが、私はこの言葉に同感した。
演奏が終わってから私たちは、思い思いの飲みものを口にしながら、歓談に時のたつのを忘れた。話題は当然音楽をめぐっていろいろに展開したが、絵画のことに話がとんだり、山中湖の自然のことになったりした。とりとめない雑談だったが、男女十人が深夜まで会話を楽しんだのだった。それこそはサロンだった。
翌朝も曇っていて、林間で紅葉を焚くというはじめの計画は中止し、明るい食堂でコーヒーを何杯ものみながら前夜からのサロン的会話を続けた。芸術における自然と人工、といったことが主な話題で、フォークナーの研究者K君が自然の尊重を主張し、ボードレールの研究者S氏が人工の価値を説き、私はその両者をなんとか綜合する立場を模索しながら喋る、といった案配で、議論は収集がつかないままうやむやになったが、それぞれが会話をたのしんだのである。そのうちに晴れてきて日が射し、窓外の黄褐色に色づいた雑木林が金色に光り、その上に富士山が姿をあらわしてきた。そして私たちは心から満足して、また連れだって帰ってきたのだった。「とてもたのしかったので、また是非誘って下さい」と別れぎわに若い女性が私に言ったので、「ええ、そうしましょう」と私は約束した。サロン・コンサートはいいものである。
 |
 |
|
 |
|
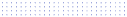 |
ペンション・モーツァルト 0555-62-3364 〒401-0502 山梨県南都留郡山中湖村平野509-38 |
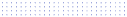 |
| |
|
|
|
|
 |